メア・アイランド
サンフランシスコに渡った咸臨丸は航海中、何日も続いた暴風雨で船体は相当傷みが酷かった。そのことを心配したブルック大尉は、勝麟太郎に親切な提案を持ちかけた。
「勝さん、今更ですが、よくこの船で荒波の太平洋を渡ってきたと驚きです。この船でまた日本に帰るためには、相当修理しないと無理だと思います。宜しければ船を修理して差し上げたいのですが、いかがでしょう。修理日数もそれなりに掛かりますが宜しいですか」
「勿論です。実はこちらから修理を是非お願いしたいと木村さんと話していたところです」
「それでは、造船所のカニンガム提督を紹介しますので、これからお会いしましょう」
ブルック大尉に案内されて、咸臨丸はこの修理のため、サンフランシスコから北東四十キロにあるメア・アイランド海軍造船所へ廻航した。ここは、広い敷地内にドックはじめ製作工場、設計事務所、武器・食料品等の保管庫、官舎等が配置された大きな造船所だった。
一行は提督室に入ると、カニンガム提督は親しげな顔で握手を求めてきた。六十過ぎの温厚な人柄だった。一通り造船所内を案内してもらうと、
「なにぶん、このような場所なのでホテルのような建物は近くにありませんが、修理の間は私の家の隣に官舎がありますので、そこを皆さんの宿泊施設としてお使いください。もし宜しければ、今夜は、わたしの家にお泊りになってはいかがですか。」
通訳の中浜万次郎は、このような時は断ってはいけないというので、勝は木村、中浜、小野そしてブルック大尉と共にお世話になる事となった。
馬車に乗り提督の屋敷に着くと、勝はその広さに度肝を抜かされた。よく手入れをされた広く一面の芝生の横に花壇があり、赤、黄、白の花が植えられ、いい匂いがした。正面にはアメリカ国旗が風に翻っている。二階建ての三角屋根には煉瓦で造った四角い暖炉の煙突が突き出している。一階には建物に付随し洒落(しゃれ)た丸柱の柵で囲むデッキがあり、豪華の中にどこか親しげな建物だった。
隣には煉瓦づくりの四階建ての官舎で別棟には自炊用の調理場と浴室が備えられていた。水を井戸から汲むのではなく、水道というものがあって、とても便利だった。乗組員は全員ここで寝泊まりする事となった。最初は帆をテント代わりにして野宿を覚悟していた乗組員達にとってこの宿舎はとてもありがたかった。
咸臨丸に積み込んであった米、味噌、醤油、梅干し、酒などを持ち込み、日本食を作ることにはまったく不自由しなかった。アメリカ人は毎日、彼らに魚の差し入れもしてくれたのだ。風呂もいつでも入れた。
この敷地内ではアメリカの士官たちも住んでおり、時折、彼らの家に招かれて歓談する内に日本人とアメリカ人の中に親しい交流の絆が出来上がっていった。
福沢諭吉も英語は読むことは少しできたが、相変わらず話すことは苦手だった。しかし、積極的に話しかける事により、徐々に彼らとコミュニケーションが取れるようになった。福沢が驚いたのは、招かれた時に奥様が出てきて客の相手をし、その間、旦那が動き回って食事の段取りをしてくれる。日本の男尊女卑や風俗習慣のあまりの違いにびっくりした。
修理は予想以上に手間がかかった。マストも前部と中央の二本を交換した。また、暴風雨で破れた帆もすべて新調した。ペンキ塗り替えなどの大掛かりな補修作業には時間を要した。勝が驚いたのは、浮きドックといわれる仕組みで一旦船を海水と共に施設内に浮かべ、徐々に海水を抜くことにより船体全てが表面に露になり、船全体が隅々まで点検できる状態にできた事だった。
アメリカの修理責任者マクジュガルは何をするにも勝に具体的な修理方法や時間の見通しを説明し、その都度、承諾を得て進めている。勝は自分たちが未熟ゆえ損壊させたものが多いので、マクジュガルさんが良いと思ったことは相談せずに独断で進めてくださいと伝えた。
ところが、キャプテン・マクジュガルから意外な言葉が返ってきた。
「勝艦長、そのような事はできません。艦長たる者は、日頃から船のことは例え甲板の板一枚といえども細部にわたって、その機能を知り抜いていなければなりません。船の各部の堅固さ、帆索がどれほどの強風に堪えられるかなど熟知していることが重要なのです。指揮官がこうしたことを詳細に知らぬばかりに、艦全体に危険が及ぶこともあり得るのです。
ですから、僅かな事でも艦長の了承のうえ修理しています。そうでなければ私は自分の仕事に安心が持てません」
勝は、修理一切を人に任せきりにした自分を恥じた。そして、この熟練の技を備え、船の事を知り尽くした達人の言葉が胸に深く突き刺さった。
更にこの作業員たちは、ありがたいことに蒸気機関(ボイラー)部分は修理の必要はなかったが、それも船体から取り外し、手入れをしてくれたようだった。
勝は勉強のためと称し水夫や火焚(ひたき)にも手伝わせた。実際、勝は製鉄所、蒸気工場、製図場どれをとっても長崎と違ったので、あらゆる技術を勉強する事ができ昂奮の毎日だった。
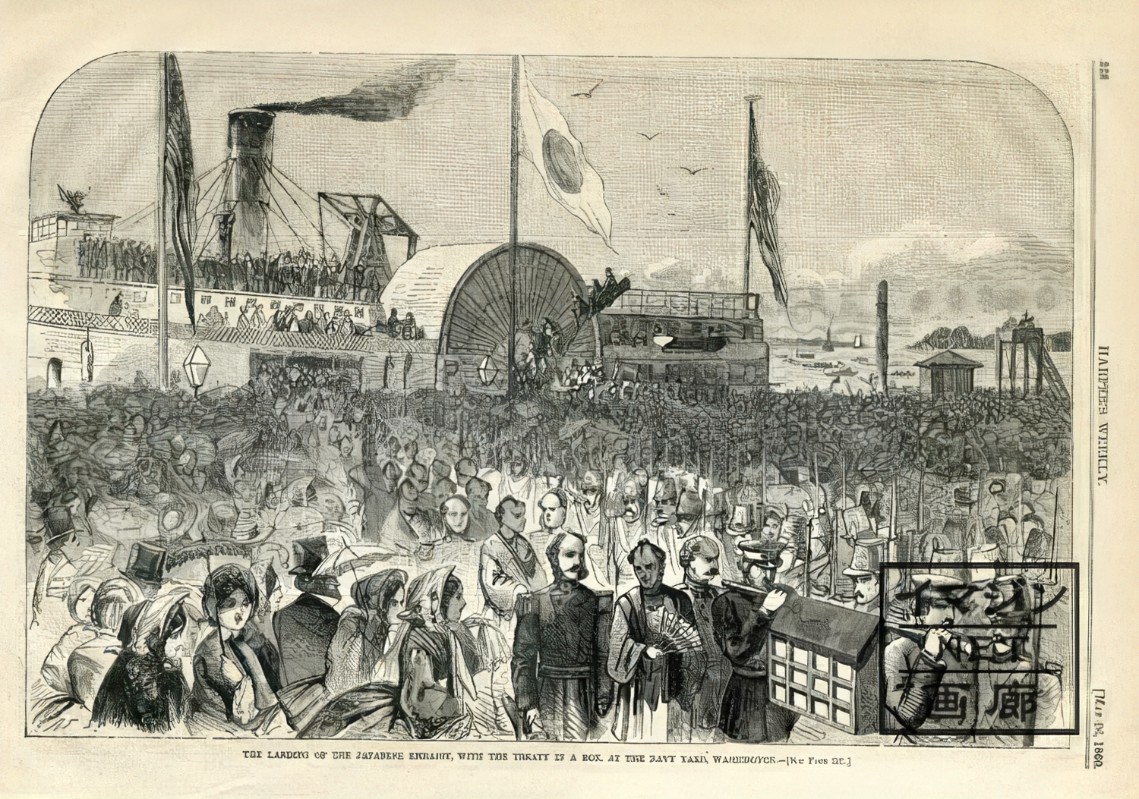





 前列中央 小野友五郎
前列中央 小野友五郎